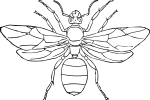朝ごはんの定番おかず、おにぎりの定番の具である鮭、その味もおいしく人気ですね!
私も好きで最低でも週に1回は食べていると思います。
見た目もあの赤色よりのピンクが白米の白色と良い感じで食欲をそそりますね。
さて、見た目は赤色なので鮭は赤身魚と勘違いしたことがあるのではないでしょうか!?
ご存知かもしれませんが、実は白身魚ですね!
知った当時は衝撃でしたが、なぜ白身魚なのでしょうか?
今回はその理由と関係してくる鮭の栄養素の秘密に迫りたいと思います!
それではどうぞ!
赤身魚はなぜ赤い?白身魚との違い
まず鮭はいったん忘れて、白身魚と赤身魚の違いについて抑えていきましょう。
まずわかりやすい違いとしては色ですよね!
赤身魚は、赤色
白身魚は、白色
です。
では赤身魚はなぜ赤いのでしょうか?

赤いもととなっているのは色素タンパク質と呼ばれるものです。
色素タンパク質ってなに?
という話ですが、ちょっと専門的な用語で言うと2種類あって
・血液色素タンパク質のヘモグロビン
・筋肉色素タンパク質のミオグロビン
になります。
名前からわかる通りわかりやすくまとめると血液と筋肉ですね。
このことから赤身魚は白身魚に比べて多くの血液の循環、筋肉を持っています。
なぜ多く持っているのか?
生きていくために必要だからなんですね。
赤身魚の例としてマグロ、カツオ、ブリといったものが挙げられますが、これらの魚は回遊魚と呼ばれ遠くまでずっと泳ぎ続けます!

もっと印象的に言うと寝てる時も泳ぎ続けます!
このため、持久力が必要なので、多く血液を循環させる、また泳ぎ続けるための筋肉が必要なんですね。
では、反対に白身魚はどうでしょうか?
遠くまで泳がない、つまり近場をゆっくり泳ぎます。
そのため、赤身魚に比べて血液の循環も筋肉量も低いです。
筋肉量が多い分、赤身魚の方が身が引き締まっていて味が濃くおいしいと言われています。
※好みはあると思いますが
では白身魚よりも赤身魚を食べた方が良いの?鮭よりもマグロを食べた方が良いの?というところに関しては後ほど触れます。
鮭が白身魚である理由
さて、それでは着目を肝心の鮭に戻しましょう。赤身の赤は、色素タンパク質と呼ばれる血液の循環と筋肉の2つのタンパク質であることはわかりましたね。
でも鮭は白身魚、じゃああの赤はなんなのさ!?と思いますよね。
これもまず専門的な言葉で言うと
アスタキサンチンという赤色の色素
です。
難しい言葉はおいて、シンプルにとらえると赤色の色素です。この色素を含むエサを食べて体内に蓄積することによって身が赤くなります。

また、鮭は生態として回遊魚ではありません。このことから白身魚でありながら赤色の身をしているというわけです。
身が赤くなるほどエサを食べるの?と疑問に思われたかもしれませんのでその部分にも触れておきます。
鮭は川で生まれ、海で育ち、その後産卵のために生まれた川に戻る習性を持っています。

生まれた川に戻る際は、川の流れに逆らって逆流の中を上っていくことになります。このため、とっても多くの体力が必要になるため、身が赤くなるほどのたくさんのエサを食べるというわけですね。
鮭の持つ栄養素の秘密
先ほど赤身魚の方が、身が引き締まっている、味が濃厚でおいしいと言いましたが、白身魚(今回は鮭を取り上げます)が勝る部分はないのでしょうか?
あります!
しかも近年は女性だけでなく男性も気にする美容に効果があります!

鮭の身の赤さのもとである赤色の色素のアスタキサンチンですが、この色素は体内の有害な活性酸素を取り除いてくれます。
活性酸素の何が有害か?ですが、身体を酸化させてしまうところにあります。
酸化、目に見えるわかりやすい例だと鉄が錆びるあれですね。

身体が錆びついた結果、老化に繋がります。
そんな有害な活性酸素を取り除いてくれるので老化防止になります。
メジャーな抗酸化作用の栄養素としてビタミンEがありますが、鮭に含まれているアスタキサンチンの抗酸化作用はビタミンEのなんと約1000倍となっています!
※なお、鮭にもビタミンEは含まれています
どうでしょうか?赤身魚よりも魅力的に見えてきますよね?
魅力的なんです!おいしく食べられる上に美容にも良いと良いこと尽くしな魚となっています!
最後に
見た目は赤いのに白身魚の鮭、その理由と鮭の赤色の秘密、赤色の栄養素の秘密までをまとめました。
ポイントはアスタキサンチンですが、この名前を覚える必要はあまりないと思います。
一文でまとめるなら
鮭は抗酸化作用がとっても高い赤色の色素を持っているから身が赤く美容にも良い
といった感じでしょうか。
まとめっぽくなりましたね。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。